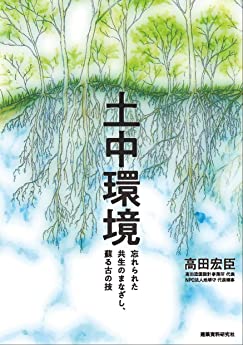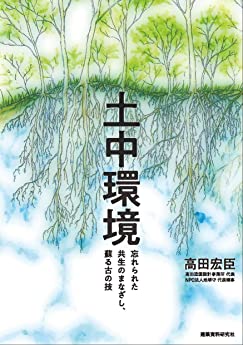
「土中環境 忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技」著:高田宏臣(たかだひろおみ)
まとめ&メモ(重要な本だったので、勉強がてらにシェアします)
第一章 01
土中環境への目覚め
●山の荒廃とはどんな状態こと?
クズなどのツル性植物や、イネ科やバラ科の荒れ地に生える雑草ばかりが繁茂するヤブ状態になること。
「植生は荒れ果て、地表は乾燥し、以前のしっとりした山肌の心地よさは見る影もなく消えてしまった」
○感想:畑の耕作放棄地もこれに近い所がありますね。経験的には、そういう放棄地の地中にはゴボウのような根っこが多くて、とても耕せません。
荒廃した土地で、いきなり不耕起の自然農は出来ませんでした。
作物が負けてしまうのです。
なので、長期間の耕作放棄地の場合は草刈りをして、畝は表面5〜10センチくらいは耕しました。
何年かすると草の勢いも落ち着いてきて、作物も育つようになりました。
●山が荒廃する原因は何でしょう?
土木建設工事による水脈の遮断と、それに伴う土中の水と空気の流れの停滞が招く、土中環境の変化。
「ある日突然、擁壁の上のケヤキの大木が根こそぎ倒れたと連絡を受けた。
それは裏山の環境を守ってきた樹齢100年ほどの大木。
根の状態を見ると、あれほどの大木にもかかわらず、地下1.5m程度より下の根は枯渇し、消え果てていた。」
○感想:こうなると台風や大雨などで、土砂崩れ等の災害が起きやすくなるのではないでしょうか。
原生林に近い状態を再現する必要があるんですね。
●なぜ大木の根が消えていたか?
根が張り付いていた岩盤が水脈の停滞によって乾き、岩盤の亀裂に伸ばしていた無数の細かな根が枯れてしまい、大木はその急激な環境変化に対応できずに剥がれ落ちるように倒れた。
この事態を目の当たりにして、環境は土中で繋がっていることに気が付いた。
道路やダム、トンネルといった現代の土木建設による構造物が土中の環境を変えている。
人間が広範囲の環境の実態を壊してしまうという実態に気が付き、
「その土地に暮らす人々にとって安全で豊かな環境を保つためには、見えない土の中から健康な状態を保たねばならない」
との思いから、荒廃した環境の再生に取り組み、すべての技術、知識、先入観を見直していった。
現代の建設土木は、崩れる事で地形を変えて安定しようとする自然の働きを許容することなく、
より大きな重量と力で押さえ込もうとする構造力学的な発想を中心に対処しようとする。
その結果として、自然環境はますます荒廃し、豊かさを失っている。
大型機械のない時代、土木造作では、地形自らが安定していくように仕向ける工夫がなされていた。
それは土中環境を健康に保つことで、無理に押さえ込むのではなく自然の作用で自ずと安定していくような配慮と造作だった。
現在では、健康な大地本来の浄化機能、貯水機能などの大切な働きを失った土地の広域化は進むばかりだ。
○感想:僕達人間は自然と共生していく道を模索していかなければならないと思いました。
その為にまずは、「知る」ことからはじめましょうよ。森の事、土の中の事、農業の事。
それは、もしかしたら現代文明の在り方を根本から見つめ直す必要があることかも知れないなと思いました。
分業が進んだ現代では、林業や農業従事者は圧倒的に少ないです。
分業の方が効率はいいかも知れませんが、自然と共生するという最も大切な事が、どんどん色褪せてしまうと思います。
地球の波動が変わりましたから、これからの世は、自然に逆らわないで、むしろ共生していく生き方をした方がいいと個人的には思いました。
また続きを書きます!
ありがとうございました!